在学生からのメッセージはこちら
長嶺成乃輔 さん

株式会社リクルート
・事業内容
株式会社リクルート,私が所属しているのはHRエージェントディビジョン。中途採用のキャリアアドバイザーとして求職者の転職活動支援を行っています。キャリアアドバイザーは、求職者との面談を通じて、転職することで叶えたいゴールを描き、目的の実現に向けて企業とのマッチングや面接対策など、求職者の大事な人生の選択のタイミングに関わるやりがいのある仕事です。入社後は、九州エリアの求職者を担当。現在は全国横断組織にて、東名阪以外の地域に住む製造業に従事している方の転職活動を支援しています。また、リクルートには多種多様なプロジェクトが存在しており、小中学生を対象としてキャリア教育支援プログラムの企画・運営にも参画しています。
・地域創生学群での学びと現在
所属していた小倉活性化PJでは、WEB媒体に社会人取材記事を掲載する活動や、グリーンバード、まちなかコンシェルジュ活動など、幅広く活動していました。その中でも、当時は学生団体として独立していた「idea+」にて、講座コーディネーター兼ファシリテーターとしての活動に力を入れていました。(のちに実習化)様々な講師を招き、そのテーマに興味がある参加者と一緒に学びを作る。内容によっては、自分自身が講師となり講座運営を行っていました。実習外では、東京にあるNPO法人の誘致・運営しているアメリカの教育団体主催のワークショップ運営にも関わっており、学生ボランティアの募集から研修、当日のワークショップ運営を行っていました。
学群時代の学びで一番大きかったのは「振り返りの大切さ」です。私は、やろうと思ったことに対する行動力には自信があり、興味があることはとことん挑戦する。そんな学生だったと思います。ただ、やったらやりっぱなしで、振り返る力は当時あまりありませんでした。そんな中、眞鍋先生や当時特任教員だった福岡テンジン大学学長の岩永さんより、実習や実践の場を通して振り返りの価値について教えていただき、いかに経験を学びに変えられていないか実感しました。リアル就職プログラムでは、インターン先の上司から「こんなのは振り返りじゃない!」と毎晩ご指導いただき、自分の中での学びの型を作っていくことができたと実感しています。
学群は、他大学や学部にはない良さをたくさん持っている環境だと思います。ただ、大学という環境で学べることは限られていると私は思います。「地創だから成長できる。」この学部にいると、ある一定までは成長を感じられると思います。しかし環境に期待を寄せ過ぎてしまうと、人間はいつの間にかそこが心地良くなり、それ以上を求めようと動けなくなってしまう。学びが止まってしまうのです。だからこそ、学群で学んだことを持って外に出ましょう。他大学の学生や、まちで活躍されている方、様々な人と出会い、学んだことを共有し合う時間を作ってみてください。心地いい、は怠惰の始まり。やるか、超やるかの精神で、大学生活の学びを最大化させてください!もちろん、大学生ならではの思い出も、たくさん作ってください。
大西彩耶 さん

北九州市公立小学校教員
北九州市の公立小学校で教員をしています。小学校教員の仕事は、授業や学級経営、学校行事の運営など多岐にわたります。やりがいは、なんといっても子どもたちの成長を間近で見守り、その成長を支えることができるということです。子どもたちが社会性を身につけ、人として成長していくことができるよう、一人ひとりに寄り添う親身な姿勢で関わることを大切にしています。日々の授業の中で、「できた!」「分かった!」と目を輝かせる子どもたちの笑顔は、教師にとって何よりの活力剤です。授業力を磨きながら、毎年、新たな子どもたちとの出会いを楽しみに働いています。
・地域創生学群での学びと現在
地域創生学群を卒業した私が伝えられることは、入学してよかった!ということです。「ひと味違う大学生活」を送りたいあなた!そんな人には、地域創生学群がピッタリです。「なんかやってみたい。」それでいいと思います。その「何か」を知るために必要なのは、行動力だけです。大学生活は自分のことを見つめる時間だと思います。たくさんの人に支えられ、たくさん経験してください。ここで自分の課題や強みを発見してください。経験した人だけが感じることができる達成感があります。それは、社会に出てきっと役に立つはずです。みなさんのことを、心から応援しています。
行徳亜美 さん

デジタル市役所推進室
DX推進課
・事業内容
私は、デジタル市役所推進室で使用する予算作成や部署内の人事関係の仕事をしています。デジタル市役所推進室では、2040年問題(人口減少、生産年齢人口の減少に伴い経済維持が難しくなること)に備え、機械に適切に頼ることで今と同じようなサービスを展開できるように市役所で行う手続きのDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進しています。
※DXとは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革すること。(NTTコミュニケーションズ参照)
・地域創生学群での学びと現在
・地域創生学群生時代に力を入れたこと
私は高校生の頃に「東日本大震災関連プロジェクト」の大学生が被災地の方々との関わり方を教えてくれたことをきっかけに、大学で「東日本大震災関連プロジェクト実習」に所属するために入学しました。そして大学に入学して希望のプロジェクトに入ることができたため、実習に最も力を入れました。東日本大震災関連プロジェクトは被災地の支援として半年に1回(1回に1週間ほど)東北を訪問します。限られた時間で被災地支援を行うにはチームワークが重要で、被災地から数年間経っても漁業や農業支援で力仕事も多く、体力づくりやチームビルディングが必要です。そのため、平日は東日本大震災関連の活動をして、休日は猪倉実習生に混じり、農作業をして体力づくりやチームビルディングをしていました。また、大学の隣にある陸上自衛隊の方からスコップやチェーンソーなどの機械の動かし方も習いました。
※現在、東日本大震災関連プロジェクトという実習はございません。
・学群での学びの何が、今に繋がっているのか
地域創生学群で学んだこと全てが今につながっていると実感できていますが、強いて言うのであれば…挑戦力と行動力です。地域創生学群のスローガンに「なければつくればいい」とありますが、地域創生学群での活動は自分たちで1から考え実践し、振り返りを行うPDCAのサイクルが重要です。仕事においても新しいことを始める時に何が課題で、どのように解決していくのか、上司に説明をして予算を付け実行に移していく必要があります。新しいことを始める、今まで通りを変えるというのは非常に時間も労力もかかりますが、地域創生学群で培った挑戦力と行動力のマインドを常に忘れず持ち続けることで自分らしい仕事のやり方を見つけられていると思います。
・先輩からひとこと
地域創生という経験ができることは学生だからこその環境のため、学生のうちにたくさん失敗して、大いに挑戦してください。そして、選択肢を選ぶ際に迷ったときは自分がワクワクする方を選んでみてください。動かないことはとても楽です。動けば動くほど大変なことは多いかもしれないけど、振り返った時に経験になっているのは大変だったことの方が多いです。この4年間は本当にガムシャラに突っ走ってください。その後についてくることは必ずあります。ぜひ頑張ってください!
河野真央 さん

・事業内容
小倉北区で『大人が集える和風カフェバー』をコンセプトに「café&bar Sui」を経営しています。「大人のサードプレイス」となり、人と人がつながることができる場にすることをテーマに学生時代に飲食のアルバイトで培ったノウハウやお店をオープンする前に働いていた法律事務所や福祉の業界、納棺師など様々な業界で働いた経験を生かしながら様々な方の居場所となるお店作りをしています。集団に疲れた方やあらゆるしがらみから逃れたい方が1人で来てゆっくりとお酒を楽しむことができる、お一人様推奨店でもあります。和の空間でおいしいお酒とおいしい和菓子から和風スイーツやおつまみが堪能でき、まったりと時間を過ごすことのできる場所を作っています。
・地域創生学群での学びと現在
・地域創生学群生時代に力を入れたこと
学生時代は様々なことに力をいれました。とにかくやってみたいと思ったことはなんでも挑戦しており、授業の後に募集されていたキャリア教育系のボランティアにも興味を持ち、活動を続けていました。それが3年生になってからチャレンジプログラムのリアル就職プログラムとしてすることにもつながりました。またサークル活動として演劇研究会に所属して裏方として年に2回の公演会でサポートしていました。大学4年生では周りが就活をしている中、夏休みに東アフリカのケニア共和国に行き、マサイ族の暮らしを2泊3日で経験したり、マサイ族で第2夫人になった日本人女性と出会って話を聞いたり、有意義な経験をしました。
・学群での学びの何が、今に繋がっているのか
地域創生学群で学んだことは全て今につながっていると感じます。実習で猪倉実習に所属していたため、地域の方とのコミュニケーションをとる機会が多く、コミュニケーション能力や先輩・後輩、地域の方との距離感も学ぶことができました。また、聞き9割、話す1割ができるようになり、聞き上手にもなったと感じています。café&barを始めて、お客様のお話を聞くことや、お客様との距離の取り方にもつながっていたり、以前、納棺師として働いていた際は亡くなった方のご家族と思い出話をしてどんな方だったのかなどお話を聞き、故人が家族と一緒に過ごす最後の時間のお手伝いをする際にもつながっていました。
・先輩からひとこと
大学時代はいろいろな経験をしておいたほうがいいです。社会人になったら時間もなくなり、できないことも増えます。できるうちにやってみたいと思ったことにはなんでも挑戦してみてください。また、色々な人と関わる経験はとても勉強になります。いろんな活動に参加している人に話を聞いてみたり、海外の文化を体験してみたり、様々な価値観に触れて自分が大事にしたいことを探ってほしいです。
二島朋美 さん

こどもふれあい本部
インタビュー動画はコチラ!
・事業内容
主に西日本新聞朝刊の中にある「こどもタイムズ」面の販売促進を行っています。また、新聞記事を読んで親子で会話をして子どもたちの「考える力・考えを伝える力」を育てるメール配信サービス「10分トレーニング」の運用や、親子向けの新聞活用ワークショップの実施、小中高大学への新聞活用の出前授業などを行っています。
・地域創生学群での学びと現在
・地域創生学群生時代に力を入れたこと
2つの実習活動です。1つ目の猪倉農業関連プロジェクト(現猪倉実習)では、土日は地域の方たちとの農作業を行い、月に1、2回はサテライトに宿泊をして活動を行っていました。まちづくり班として高槻まちづくり協議会との関わりながら活動を行っていました。2つ目の東日本大震災関連プロジェクトでは、 46次派遣で 3回、宮城県南三陸町へ訪れました。
※現在は所属できる実習は1つです。
※東日本大震災関連プロジェクトは現在はございません。
・学群での学びの何が、今に繋がっているのか
大学で経験したこと、学んだこと、感じたことすべてが今につながっています。学群では、どんなことでも与えられた場所や環境でしっかりやって学び取ると言い聞かせて取り組んできました。現在も自分のやりたいことだけに目を向けるのではなく、まずは何事もやってみる姿勢を持つことを心がけています。また、実習活動の一環の南三陸町への派遣を通して新聞の役割と必要性を感じたことから西日本新聞社を志望しました。学群での経験があったからこそ、現在の仕事に繋がっています。
・先輩からひとこと
地域創生学群では実際に地域に出て活動することができ、色々な経験を積むことができます。そこからたくさんの人と出会い、たくさんの学びがあります。それを自分の中に落とし込んでさらに自分が本当にやりたいことに繋げられる学群だと思います。皆さんもぜひそういったところを思い描きながら地域創生学群で頑張っていただきたいです。
若杉奈々子 さん
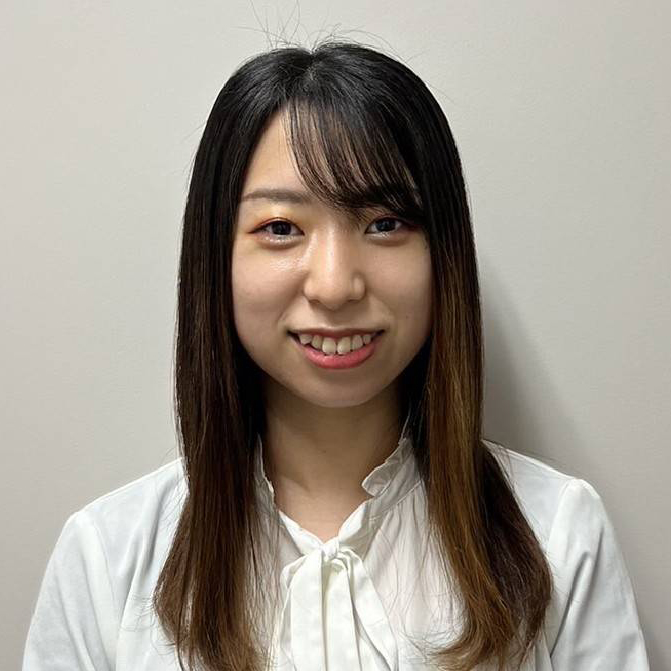
保護第二課
インタビュー動画はコチラ!
・事業内容
みなさん、漫画やドラマでも放送された「健康で文化的な最低限度の生活」を知っていますか?私はそのドラマの中で主人公が演じていた生活保護のケースワーカーをしています。私の所属している保護課は、日本国憲法25 条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障し自分の力で生活できるよう支援する制度に基づいて業務を行っています。私はケースワーカーとして、受給者の方が適切な制度を使えるようにしたり、相談や支援を行ったりしています。
・地域創生学群での学びと現在
・地域創生学群生時代に力を入れたこと
実習活動とゼミ活動です。地域の方と密になって交流したりコミュニケーションをとったりするのは学群ならではの活動だと思いますので、積極的に取り組んできました。ゼミは廣川ゼミに所属し、フットパスを通してまちづくりについて研究していました。
・学群での学びの何が、今に繋がっているのか
私は1年生の頃は地域福祉コースの実習で、特に「個」に向けてのアプローチの方法を学び、現在ケースワーカーとして一人一人に合った支援の方法は何か考える力に結びついていると思います。 2年生から地域マネジメントコースのゼミへ入り、全 体を見てどのようなイベントの運営をするかを学び、現在では、全体を把握してどのように働きかけていく業務を行っていくかを考えるところに繋がっていると思います。さらに、このような実習活動やゼミ活動を通じて培った、お世話になった地域の方に恩返しをしたい、学群でのノウハウや知識を活かして北九州 市を活性化させたいという思いが現在の仕事に繋がっています。
・先輩からひとこと
地域創生学群では、貴重な経験がたくさんできる環境が整っています。ぜひ学生の内に、貴重なたくさんの経験をしてみてください!
